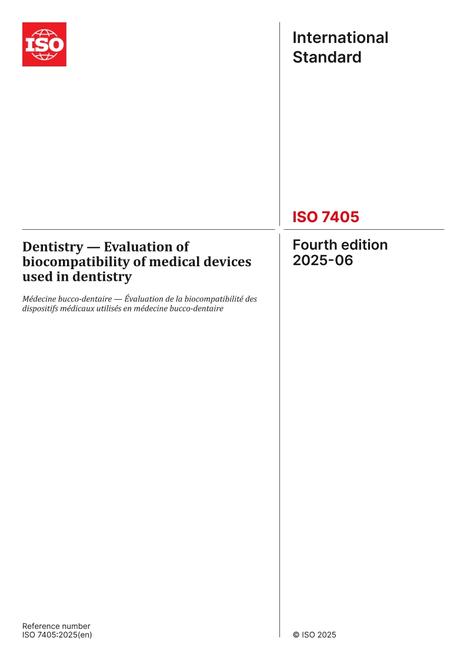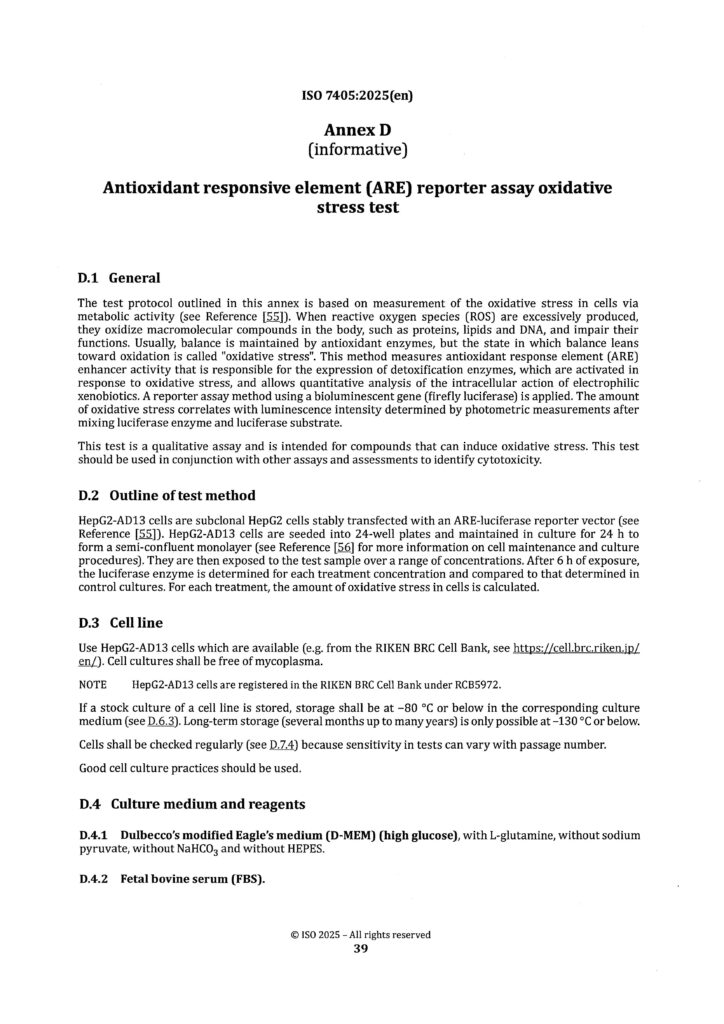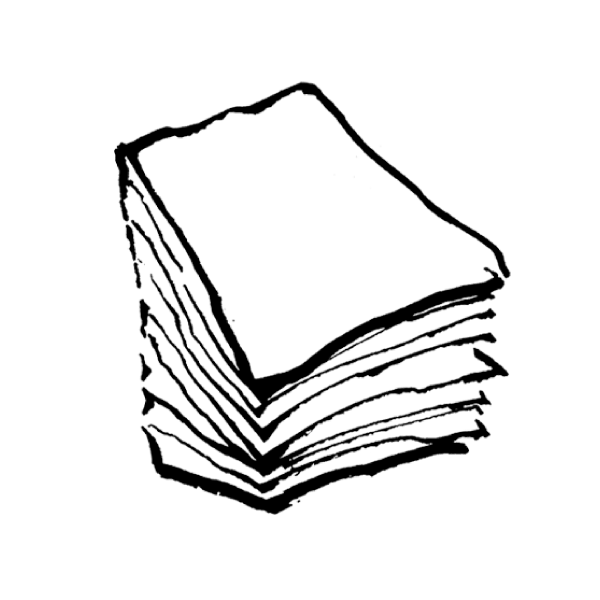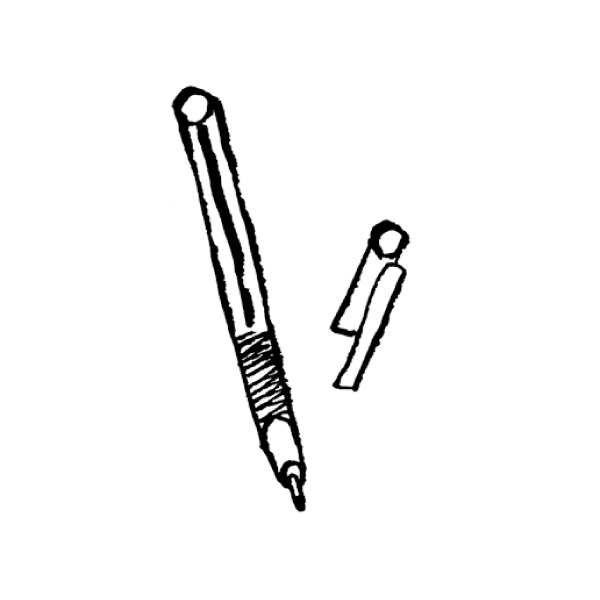研究活動トピックス
歯学部の研究成果による評価試験法が、ISO規格(国際標準規格)に収載されました
歯学部
ISO(国際標準化機構)は、国際的に通用する規格(ISO規格)を制定しており、品質マネジメントシステム(ISO 9001)や環境マネジメントシステム(ISO 14001)などが有名です。身近な例では、乗用車のチャイルドシート取付の標準規格(ISOFIX)などもあります。
このたび、歯学部歯科理工学講座と生化学講座での研究成果をもとにした Antioxidant responsive element (ARE) reporter assay oxidative stress test(抗酸化応答エレメント(ARE)レポーターアッセイ酸化ストレス試験)がISO 7405(歯科用医療機器の生物学的安全性評価法の標準規格)のAnnex D(付属書D)に収載されました。
【これまでの経緯】
本学歯学部歯科理工学講座の堀美喜講師は、2013年、本学大学院における研究として、生物発光を用いた細胞毒性試験法を用いた研究を同年の歯科理工学会にて発表しました。この試験法は、従来の「細胞の生死」を評価する方法とは異なり、「生きた細胞が受ける酸化ストレス」を定量的に測定できる点が優れており、これにより、より精度の高い生物学的安全性評価が可能であることが大きな特徴でした。
発表後、ISOのTC106(歯科)分科会委員から、ISO 7405へこの試験法の提案を検討するよう助言があり、このプロジェクトがスタートしました。
翌2014年には、当時、同講座主任教授であった河合逹志先生(現・本学名誉教授)が中心となり、TC106/WG10(生物学的評価)議長のG. Schmalz 氏(ドイツ)に対して試験法の内容を直接説明する機会を得たことにより、収載に向けて大きく弾みがつくこととなりました。
その後も継続的な実験と、国内外の複数の研究機関によるインターラボラトリーテスト(複数施設による検証試験)が重ねられた結果、2025年6月に発行されたISO 7405 第4版において、本試験法がAnnex D(付属書D)として正式に採用されました。
なお、この国際規格への採用に至るまでのプロセス(ISO会議での説明、質疑応答、試験の実施、文書作成など)は、堀講師が日本代表委員として全て担当しました。また、この試験法は、河合名誉教授と本学歯学部生化学講座の鈴木崇弘教授らとの共同研究によって構築されました。
本学の研究成果から提案した試験法が国際規格に採用、収載されたことは、研究者の長年の努力が結実した大きな成果です。
今度とも本学では、研究推進を通じた社会貢献に努めてまいります。
【参考】この試験法のもととなった研究論文
Effect of 2-Hydroxyethyl Methacrylate on Antioxidant Responsive Element-Mediated Transcription: A Possible Indication of Its Cytotoxicity
Ai Orimoto ,Takahiro Suzuki ,Atsuko Ueno,Tatsushi Kawai,Hiroshi Nakamura,Takao Kanamori
PLOS ONE 2013 March 14;3(8):58907