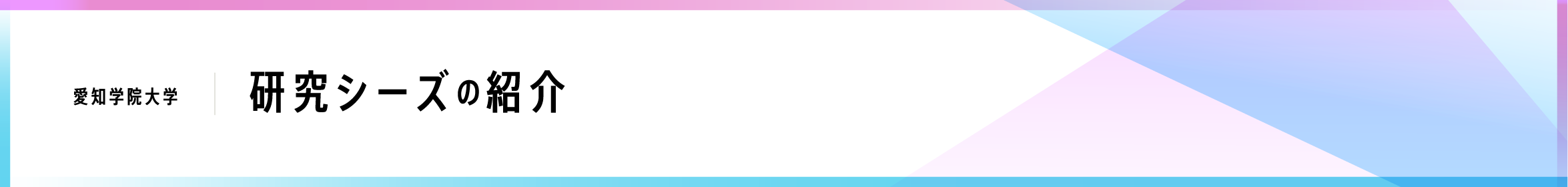ライフサイエンス
運動指導経験の有無と敏捷性との関係性についての探索的検討

長﨑 大
NAGASAKI Masaru
- 職位
- 教授
- 所属
- 健康科学部健康科学科
- 分野
-
ライフサイエンス
- キーワード
- 高齢者フレイル,敏捷性,転倒予防
- 研究メンバー
- 山本 正彦、小松 悠人、辻󠄀本 昌史、田中 誠也
超高齢化社会を迎えた現代において、転倒は要介護状態につながる重大な要因の一つであり、今後さらに積極的な転倒予防への取り組みが求められています。転倒対策としては、下肢の筋力や敏捷性(敏捷性の定義:ある刺激に対して身体をすばやく動かしたり、方向を変えたりする能力)を高めることが重要であるとされています。これまでの研究から、敏捷性は加齢とともに低下することが明らかになっていますが、継続的な運動により、敏捷性の維持や低下の予防が可能であることも報告されています。
日常的に運動を実施している人の中でも、とりわけ運動指導の経験を有する人は、指導対象者の動作を詳細に分析し、修正すべきポイントを見出す力や、模範的な動作の提示といった高度な技能が求められます。そのため、一般の運動実施者に比べて、より高いレベルで敏捷性が維持されている可能性があると考えられます。しかしながら、運動指導経験の有無と敏捷性との関連性については、これまで十分に検討されておらず、不明な点が多いのが現状です。
そこで本研究では、運動指導経験の有無によって敏捷性にどのような特徴が見られるのかを調査し、運動指導経験と敏捷性との関係性について明らかにすることを目的としています。
アピールポイント(長所・差別化ポイント)
超高齢社会が急速に進行する日本において、社会保障費や医療費の増大、労働人口の減少といった構造的課題が深刻化しています。特に転倒は要介護状態へとつながる主要な要因であり、その予防は健康寿命の延伸と地域包括ケアの実現に不可欠な取り組みです。
本研究は、転倒リスクを単に身体機能にとどまらず、筋力・平衡性・敏捷性・認知機能・生活習慣といった多角的視点から総合的に評価し、科学的根拠に基づいた転倒予防プログラムの開発を目的としています。こうした取り組みは、個々の高齢者のQOL向上に寄与するのみならず、地域全体の医療・介護負担の軽減にもつながる社会的意義の高いものです。
本研究は、国立長寿医療研究センターとの共同研究として推進しており、今後は名古屋市や地域スポーツクラブとの協働を通じて、地域密着型の転倒予防講演やデータの収集を展開してまいります。こうした産官学連携による取り組みにより、実用性と汎用性を兼ね備えたモデルの構築を目指します。
得意な技術・提供できる技術
視覚認知と筋機能を含む細分化された敏捷性機能測定
研究シーズ 一覧に戻る