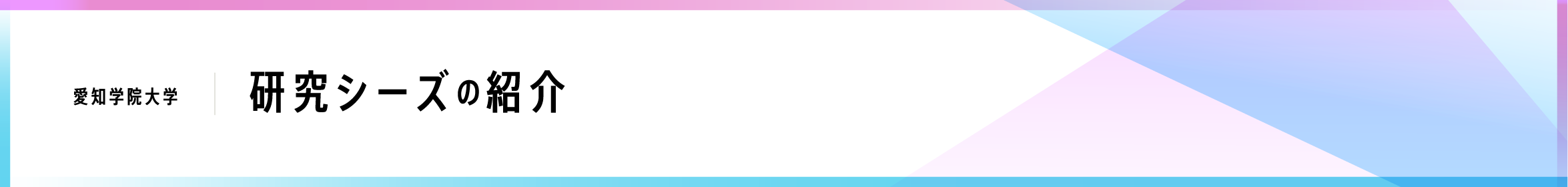人文・社会
Telepractice(遠隔言語治療)口蓋裂言語の言語療法,22q11.2欠失症候群患者の移行期支援

早川 統子
HAYAKAWA Touko
私の研究は、言語聴覚士としての臨床経験を基に、以下の3つの主要なテーマに焦点を当てています。
1. 口蓋裂言語の臨床
口蓋裂のある子どもは、構音(発音)障害や鼻咽腔閉鎖機能不全によることばの障害を経験することがあります。彼らには適切な評価と介入が必要です。私は口蓋裂児の音声・言語発達を評価し、効果的な介入方法を確立することを目的として研究を進めています。特に、構音評価の指標の開発や、個別化された言語療法の有効性を検討しています。
2.Telepracticeの活用
遠隔医療(Telepractice)は、地理的制約を超えて言語療法を提供できる手段として注目されています。私は、口蓋裂児やその他の言語障害を持つ子どもに対する遠隔リハビリテーションの有効性を検証し、対面療法との比較を行っています。また、遠隔評価システムの開発や、保護者との協働による家庭支援プログラムの設計にも取り組んでいます。
3.22q11.2欠失症候群患者の移行期支援
22q11.2欠失症候群(22qDS)の患者は、小児期から成人期にかけて多様な医療・教育・社会的支援が求められます。特に、思春期以降の移行期において、適切な医療・福祉サービスへのアクセスが課題となっています。私の研究では、22qDS患者の言語・認知特性を明らかにし、成人期へのスムーズな移行を支援するための包括的プログラムの構築を目指しています。
今後の展望
今後も、口蓋裂児や22qDS患者の言語・発達支援の充実を図るとともに、Telepracticeを活用した遠隔リハビリテーションの発展に貢献していきたいと考えています。また、研究成果を臨床現場や教育の場に還元し、言語聴覚療法の質の向上に努めてまいります。
この研究を通じて、より多くの人々が適切な言語支援を受けられる環境を整え、社会全体の福祉向上に寄与することを目指しています。
アピールポイント(長所・差別化ポイント)
私の研究の強みは、臨床・研究・教育を有機的に結びつけ、実践的な課題解決に貢献することです。
研究シーズ 一覧に戻る