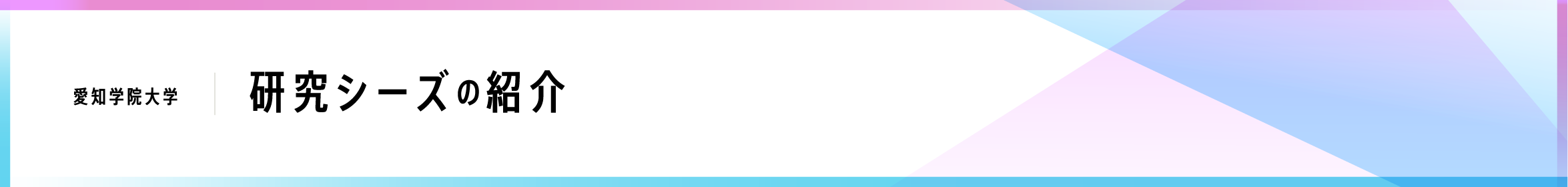人文・社会
選択体系機能言語学を用いたテクスト分析と英語教育

佐々木 真
SASAKI Makoto
- 職位
- 教授
- 所属
- 教養部
- 分野
-
人文・社会
選択体系機能言語学は社会の中で、どのように言語が機能するかを模索する理論です。誰もが母語での言語表現を無意識のように表出したり解釈します。しかし、そこには文化的な共通認識の背景があり、同時に文化的・状況的コンテクストという制約を受けます。そして、そのような背景や制約の中、語彙と文法的パターンの選択を経て言語表現がやりとりされます。時代やさまざまな文化的要因によって言語の機能は変化し、また目的によっても言語の果たす役割は変わるのです。私の研究テーマではその中でも、日本の古典を英語に翻訳する場合の問題やニュースメディアでの言語使用、そしてそこから言語教育にどのように応用できるかを研究しています。
特許・著書・論文情報
『ことばは生きている』(龍城正明 編)(2006)、東京:くろしお出版(第8章を執筆)
『意味論・語用論と言語学諸分野とのインターフェイス』(米倉よう子 編) (2021)、東京:開拓社 (第6章「意味論・語用論と選択体系機能言語学のインターフェイス」を執筆)
和歌の英語訳:6種類の源氏物語の英語訳の比較分析」, Proceedings of JASFL. Vol. 11. pp.97-108.(2017)
「選択体型機能言語学の翻訳への応用-The Language of Schoolingの翻訳実践例-」愛知学院大学教養部紀要第64巻第1号 愛知学院大学pp.27-45 (2016)
アピールポイント(長所・差別化ポイント)
選択体系機能言語学は社会の中で、言語表現がどのように表出され、また解釈されるかを解き明かします。これは日々のコミュニケーションのみならず、ビジネスコミュニケーションでの問題点を浮き上がらせ、その解決策の糸口を提示します。また効率的な語学教育についても提言ができます。また過去にはiPadを用いた英語教育について企業と共同研究を行なった経験もあり、AI時代にどのように英語教育を行うべきか、論文や新聞への投稿記事にて提言も行なっています。
研究シーズ 一覧に戻る