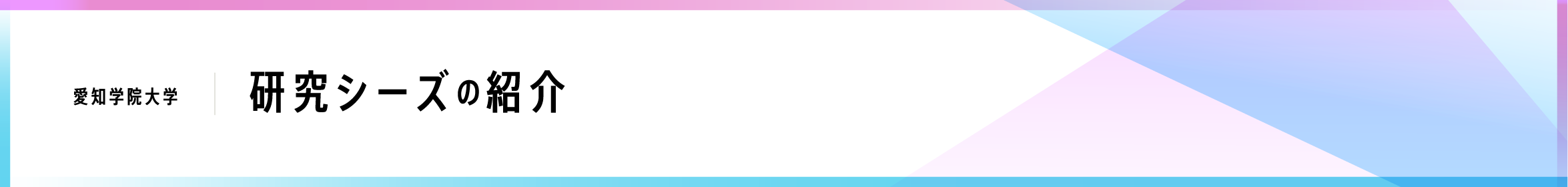人文・社会
アメリカにおける会計システムの歴史的展開

伊藤 徳正
ITO Norimasa
アメリカにおいて、1929年の大恐慌からの脱却を目指したニューディールの一環として制定された証券二法に基づき行われた会計システムの大変革が近代会計を形作ったと考えられる。証券二法に基づき、証券取引委員会(SEC)が設置され、上場企業には財務諸表の提出と会計監査が義務づけられた。当初、SECに会計原則設定の法的根拠が与えられていたが、会計原則設定の主体が誰であるべきかに関する論争があり、アメリカ会計士協会内部の会計手続委員会(CAP)によって、会計原則が設定され公表されるようになった。これらの変革は国際的に大きな影響を与えた。その後、会計原則設定の役割は、会計原則審議会(APB)、財務会計基準審議会(FASB)に受け継がれて現在に至っている。 会計原則および基準の設定者が誰であるべきかという論争が、会計原則設定主体の変遷に大きな影響を与えてきた。CAPは公認会計士のみによって運営されていたが、コントロ-ラー等が原則設定に関わるべきだとの社会的要請から、APB、FASBへ設定主体が変遷するに従い公認会計士以外にも設定に関わる職業が拡大された。当研究において、アメリカの会計システムの歴史的展開を会計原則の設定機関の観点から調査分析する。特に、国際的に大きな影響力をもつアメリカ会計原則・基準設定機関の変遷を詳細に整理することによって、どのような背景をもつ職業が設定に携わるべきかを明らかにし、現代の会計基準設定機関の抱える問題と改善点を考察することを目的とする。
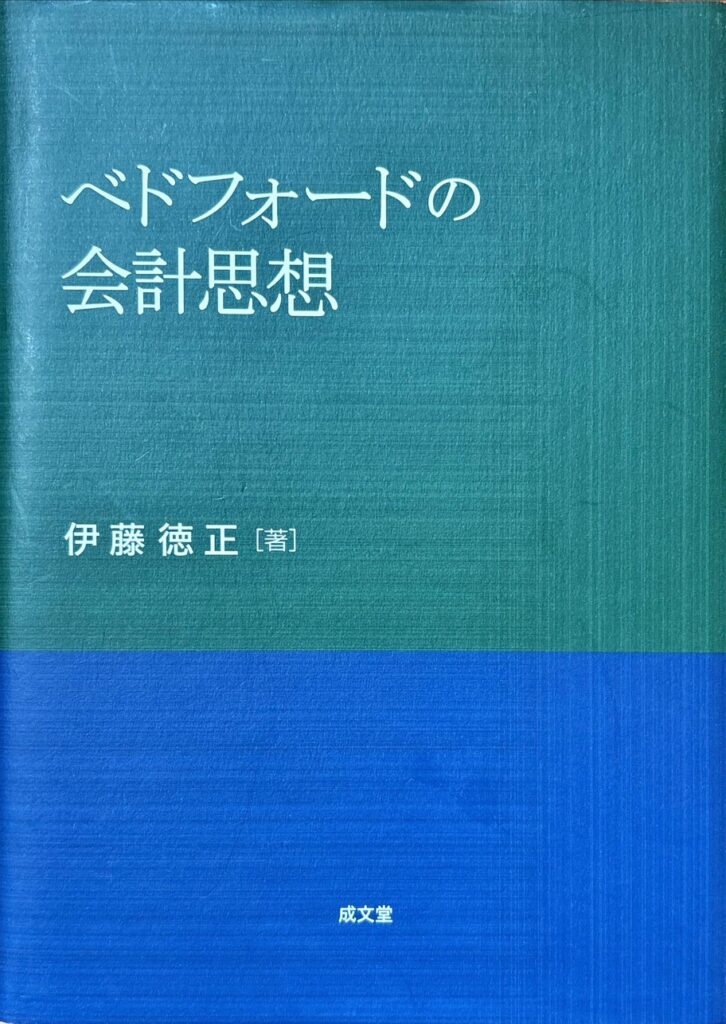
アピールポイント(長所・差別化ポイント)
現在は全世界的に会計基準の統合が進んでいる。会計基準の明文化を最初に成し遂げたアメリカを対象にして、会計基準設定機関に焦点を当てて歴史的展開を整理する。それによって、現代の会計基準設定機関の抱える問題と改善点を考察する。
研究シーズ 一覧に戻る